タンゴのDJというのは、なかなか奥深い。
そもそも他人の心の奥底をのぞいて、
あそこで踊っている二人の踊りたい曲をかけてやろうなどと
おこがましい野望を抱いてはいけない。
曲と人を知る、そしてタンダを知るということではないかと、今は思う。
<曲と人を知る>
2008年のはじめに「バイラブレ仮説」というのを書いていた。
バイラブレ仮説
http://sacadaenborde.blogspot.com/2008/01/blog-post.html
ここで前置きで述べていることが、少し最近見えてきた。
「踊りやすい」という表現は主観的なミクロな概念であって、
本来一概にどれがどうという話は出来ないはずなのに、
なんとなく共通認識として「踊りやすい」というマクロな概念となる。
どういう人が、どういう曲を、どういう風に聞くか。
現象は少し具体化する。
今考えているのは、次の3つ。
1.適度に、単調な曲
まったくの初心者はメトロノームが一番踊りやすいだろうが、
それなりに踊れる人は、複雑すぎず、単調すぎず。というラインに落ち着くだろう。
2.適度に、動きやすい曲
簡単のため、テンポだけの話にしている。
タンゴの曲平均的には、「半拍で一歩」「一拍で一歩」の感覚がとても大切だと思う。
3.適度に、聞きなれている曲
聞きなれていること。
というのは、それこそ完全に各人の経験なんじゃないかとも思えるが、
私はこう考えることにしている。
ある人があるミロンガに行くということは、
それなりに、そこのミロンガの選曲傾向が好きで、そのへんの音楽に聞きなれているものだ。
補足:日本のミロンガを見ると、このような3タイプがあるんじゃないか、という図。
この人は、あのミロンガでよく見かけるから、こっちの選曲が良いかもしれない。
でも、踊っている相手は、あちらのミロンガで見かけるなぁ。はて?どっちにするべか?
などと延々と思考を続けて、やがて考えが収束するようなところが、ねらい目だ。
<タンダを知る>
さて、短めにまとめるつもりがすっかり前置きが長くなってしまった。
なので、以下、尻切れ気味。
DJやタンダについての文献は多々あるのだが、
基本的なポイントは踊りと同じで、サプライズばかりじゃ疲れるし、無難すぎるのも飽きる。
最近いろいろ試行錯誤してみて、次のようなタンダの分類ができるのではないかと勝手に提案する。
1) Wake-up! Tanda(仮)
「そろそろ起きなさい」という意味を込めて命名。
靴を履いたり、体をほぐしたり、挨拶をしたり。
入場から15分は、なんだかんだ言って割と気分が乗らないもの。
そんな時にかけるタンダ。
あ!踊らなきゃソンソン。
動き出すきっかけになりそうな、会話を殺さない明るめの曲で、有名な曲を重ねるのがよさそう。
メロディ重視よりも、リズム重視の方がよさそう。
2) Transition Tanda(仮)
傾向を変えるときのタンダ。
で、命名。
違った傾向のタンダに速やかに移りたいときや、
生演奏・イベントなどが挟まるとき。
少し、今までと違うシグナルを混ぜる。
展開によって、選曲もいろいろ。
個人的にはトリオとかカルテットくらいの軽奏が好き。
3) Breathy Tanda(仮)
とにかく、動きたい!
そういう輩がいるかどうか。よく見ていないといけない。
いるなら、とにかくハァハァ言わせてしまおう。ほととぎす、ってことで時々使う。
カンドンベとか、速いワルツとか、フォエバータンゴやコロールタンゴみたい系統もこれかも。
4) Calm-down Tanda
しっとりと行きましょう。
メロディ重視の曲とか、30年代前半よりも古い感じ
エレクトリカなんかは、実は割りと落ち着いたりするので、使いどころかも。
生演奏の後なんかは、場合によっては一旦冷やす。
5) Collector's Tanda(仮)
日本だけじゃないと思うけど、
「今日は何だか持ってる曲ばかりで面白くないね」とかいう方がたまにいる。
そういう人には、基本的にコレクションでは適わない。
適度に、コレクター嗜好のミロンガでよくかかる選曲をちりばめよう。
6) Degeneration Tanda
縮退傾向のタンダ。とでも言うべきか。
そろそろムードを変えていきたい、とか、そろそろ客層を若めに。
などと狙っていくよりも、不本意にこういう事態が発生していることが稀に見られる。
明らかに、一部の客層の逆鱗に触れるタンダ、しかも4曲。
ということで、一部の人たちに、ほたるの光がかかっている気分にさせてしまうタンダ。
7) Last Tanda
ラストタンダは永遠に。
とにかく、残っている人向けに、とっておきの玉手箱。
個人的には最後にクンパルは大嫌い。
かと言って途中でもかけづらい。
具体例は、またの日に。






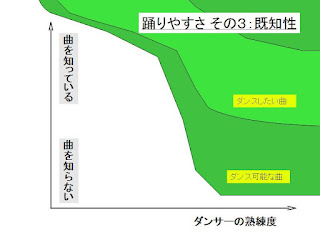

0 件のコメント:
コメントを投稿